「公文の先生になるには?説明会に参加してわかった現実と試験内容とは」
子どもと関わる仕事がしたい、教育に興味がある、家庭と両立しながら働きたい、そんな理由から「公文の先生になりたい」
と考える方は多いかもしれません。
私自身もその一人で、思い切ってKUMONの説明会に参加し、実際に試験を受けるところまで進みました。
ネット上にはさまざまな情報がありますが、やはり実際に説明会に足を運んでみると、現場ならではのリアルな話を聞くことができ、イメージが大きく変わりました。
この記事では、説明会で感じた公文の先生の現実や、選考で出題された筆記試験の内容、面接で問われたポイントなど、私自身の体験をもとに詳しくお伝えしていきます。
これから公文の先生を目指す方にとって、少しでも参考になる情報をお届けできればうれしいです。
Contents
公文の先生になるには?まずは説明会への参加から

結論:順番として
①説明会の参加
② 公文の先生になるための試験を受ける
③ 合否の結果が出る
④ 合格後、今後について説明・話し合い
⑤ 本格的に公文の先生になりたい方は詳細内容を詰めていく
と言った内容となります。
ですので、ファーストステップは!
「公文の先生になりたい」と思ったら、最初のステップは説明会への参加です。
筆者は実際に④までいきましたので、詳細を知りたい!
という方はコメントいただければ回答できる範囲でお答えいたします。
ただし、年齢制限はあるようで55歳まで!のようです。
全国の公文教室で随時開催されているこの説明会では、KUMONの教育理念や、教室運営の流れ、収入モデル、サポート体制などが丁寧に説明されます。
私が参加した説明会も非常に分かりやすく、参加者は主婦の方が多く、皆さん真剣な表情で話を聞いていました。
疑問に思っていた「未経験でも大丈夫?」 →結論:大丈夫です
「収入は安定する?」→ 集客からスタートすると安定するまですこし時間がかかるかもしれませんね。
といった点もすべて丁寧に答えていただけて、不安が少しずつ解消されていきました。
説明会は、実際に公文の先生としての働き方をイメージするための大事な機会です。
上記内容を詳細にパワーポイントで説明してくださいます。
また、個別面談も含んでいたため、上記説明でわからないこと、不安なことは随時質問ができるよう配慮してくださいました。
その中で、一点気に入ったこととして、我が子が自分の「公文」に通う場合は無料で受講できることです。
いいなぁ。と思いましたが、我が子が自分の親できちんとついてきてくれるのか?
もちょっぴり心配になりました。
こちらの説明会が終わった後に、↓以下の筆記試験へと進むことになります。
ただ、この時点で悩んでいる方にも勧めてくださいます。
合格した後に、検討してもよい。とのことでしたので、筆者はせっかくなので受けてみることにしました。
筆記試験の内容と対策ポイントについて

筆記試験は、KUMONの教材で使われる形式に近く、基本的な読み書き・計算力が求められます。
私が受けた際は、漢字の書き取りや短文の要約、算数の応用問題などがありました。
時間は60分程度で、焦らず取り組めば十分に解けるレベルと言われていましたが、正直大学院をでている筆者でもぎりぎりか間に合わないレベルでした。
具体的には以下の内容になります。
オンラインでの問題・回答でした。
全ての問題の前に、練習問題を解く時間があり、その問題でどういった問題が出題され、どう回答するのか?
を理解したら開始する流れとなります。
- ① 計数 9分 50問
- 計算問題です。
- が、かなり難しい?というか考えさせられます。
- 久しぶりに実践すると、え!なんだっけ?と考えます。
- 例:5÷11=1/3 × ○
- 1/5+3/2= 0.6 + □
- など、○と□を4択くらいから選択して回答したと思います。
- もう、びっくりするくらい時間が足りませんでしたね。
- 合っていたかも確かではありませんでした。
- ② 言語 10分 32問
- 要は国語。筆者の言いたいことは?
- と言った内容だったと思います。
- 個人的にはこれが難しかったです。
- 日本人があるが故、難しいのか?
- 国語が得意な人と仲良くなりたいレベルでした。
- ③ 英語10分 24問
- 問題文があり、その回答を「正しい」「反対」「不明」の3択から回答する問題でした。
- 問題文から英語ですので、問題が理解できていないと回答もできない問題です。
- こちらはなんとか、かんとか時間内にギリギリ終わりました。
- ④ パーソナリティ 20分
こちらは、自分自身の考えに一貫性があるか、同じような質問をされるので一貫して答えるのみです。
難しくはありません。
ただ、こちらを重要視されている可能性があります。
これら試験の後、試験結果の通達と合否、面談がある際、この内容を詳細に教えていただきました。
試験に関しては、個人的には事前に準備できることは少ないと思いますが、
事前に市販の中学生向け問題集や、公文のプリント例を見ておくと安心だと思います。
それでも成績に反映されるとは思わないレベルの問題(結構難しい?)でした。
また、採点基準には「丁寧さ」も含まれる印象を受けました。
自分の知識を再確認する良い機会にもなりました。
面談での質疑応答
ここで、やはり聞かれるのが『KUMONの理念』についてです。
こちらは事前に確認をして、共感できるところは自分の言葉にできるようになっておくことをおすすめします。
確実に聞かれます。
筆者も2回は聞かれたと思います。
あとは、共感できたところを深掘りされることもあります。
また、過去に自身もKUMONに通ったことがあるか?
その際、どう感じて今どう思っているのか?
などは確実に聞かれます。
筆者も小学校のころ、少しだけ通った経験があるので、そのことについて
率直な意見を述べました。
その点などを含めて、自身の子供にも習わせたいか?
筆者の場合、こちらの試験を受ける前にお試し入学?
を我が子にさせて、子供が「通ってみたいと」
と自分の意思を示していたので、ちょうど入ったばかりでしたので、そのことをお伝えしました。
そちらのKUMON教室のことも、面接官らは周知しておりますので、嘘なく正直に答えるのが望ましいですよ!
結果、『合格』しましたが、現実的に今KUMONの先生になることは難しいため、タイミングをみて、本当に実践したい。
また、その資金が揃った時に考えたいと思います。
公文の先生に向いている人とは?説明会で感じた共通点
説明会に参加して感じたのは、公文の先生を目指す人にはいくつかの共通点があるということです。
たとえば「子どもが好き」
「教育に関わる仕事がしたい」
「家事や育児と両立しながら働きたい」
という思いを持っている方が多く見受けられました。
特に主婦の方が多く、「ブランクがあるけれど何か始めたい」
という方にも公文の仕事は魅力的に映っているようでした。
子どもと接する仕事なので責任感は必要ですが、教える内容が決まっているため安心感もあります。
私も、「特別なスキルがなくても挑戦できる場」であることに大きな魅力を感じました。
未経験でもできる?実際に働く公文の先生の声
説明会では、実際に教室を運営している現役の先生からのお話を聞く機会もあるようですが、まだまだコロナ明け、オンラインでは直接話を聞く機会はありませんが、説明は十分担当の方がおこなってくれました。
その中で印象的だったのは「最初はみんな未経験だった」という言葉です。
公文では、開設前後に丁寧な研修制度があり、指導の基本から教室運営、保護者対応までしっかりサポートされます。
また、教室開設後も地域の先輩先生や担当者のフォローがあるため、一人で悩むことは少ないとのことでした。
実際に現場に立ってからがスタートだという考え方が、背中を押してくれました。
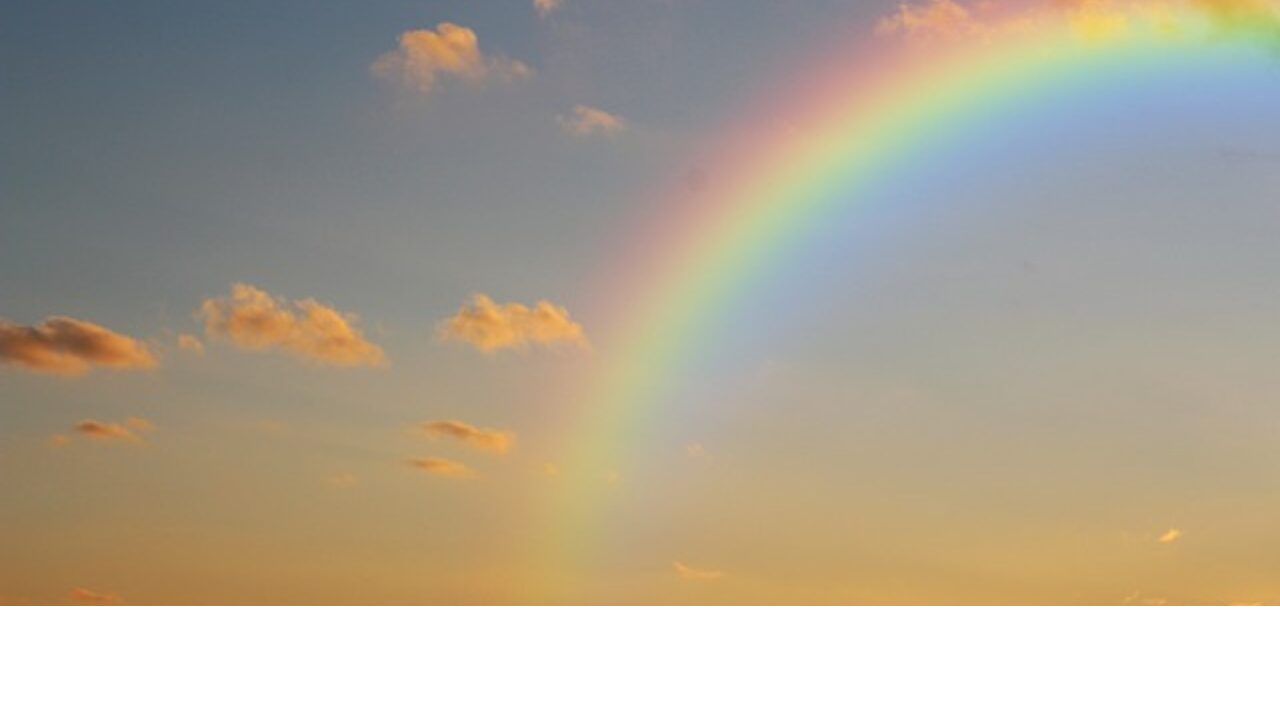

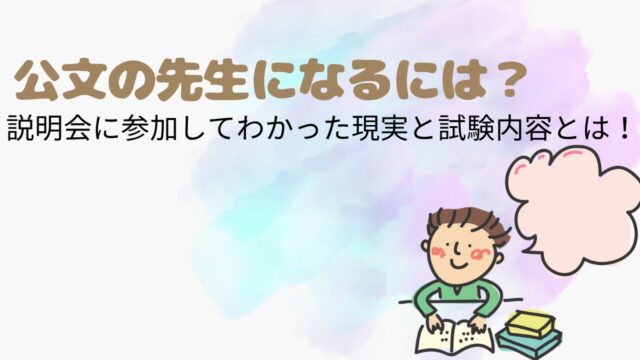


コメント